金のなる木 五円玉

金のなる木とは海外ではパキラの
ことがmoney treeと一般的に呼ばれています、こちらも
金運に関連する植物として有名です。
日本ではクラッスラ属の多肉植物
学名はC.portulaces
クラッスラ・ポルトゥラケア
のことで金のなる木と俗称などで呼ばれるのが一般的です。
自生地は南アフリカですが、ある程度の大きさに
成長すると、わりと寒さには強い多肉植物です。
ほんの少しの雪などは、葉が霜に少しやられるぐらいで枯れることは少ないです。
花月(かげつ)という品種のものが一般的です。

日本では花は3月~4月ごろに咲きます、桜のシーズン
なので、やや印象が薄いですが
近くでみるとなかなか華やかな感じはする
ものです。
葉が肉厚で硬貨のような形をしている
のも特徴です。
多肉植物なので強くさわっただけでもわりと
葉がおちますが、普通のことです。
別名は「成金草」などとも。
金のなる木などの多肉植物はあまり成金の人が持つというイメージはないですが。
しかし日本の億り人というのは
着ているものはユニクロ。またラルフローレン
自動車はトヨタヴィッツとか日産ノート
週末、家族と一緒に木曽路で食事
などという、ひとが多いようなので
ある程度裕福な人がもっていても
おかしくはないという感じもします。
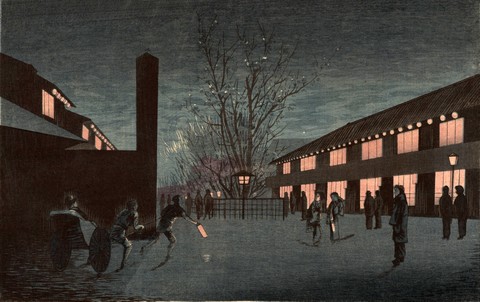
本筋とはそれますが、吉原の夜桜のことも
金の成る木といわれていたようです。
② 吉原の夜桜の異称。
※雑俳・柳多留‐三〇(1804)「金の成る木を駒下駄でながめてる」
出典 精選版 日本国語大辞典
この吉原の夜桜1ヶ月間の花見の為に
かなり大盤振る舞いしていたようで。
金の成る木と呼ばれるのも納得できます。
毎年花見の時期に合わせ、わざわざ千本もの桜を移植していたのです。さらに、1ヶ月の花見期間が終ると、花が散った桜をそのままにしておくのは無粋と、全て取り去っています。これを請け負ったのは高田の長右衛門なる植木職人で、費用は150両。現在に換算するとおよそ1500万円!
出典 https://ameblo.jp/masanori819/entry-12365826279.html
話の本題、金のなる木ですか五円玉と
よく結びつけて言われることがあります。
まだ若い方は、ほとんど実際には見たことがないと
思うのでよくある多肉植物の一種と五円玉とはなかなか
不思議な感じがするのではないでしょうか。
この由来は、金のなる木に五円玉を通すということが
昔流行った時期がありました。
渡来は昭和初年。一時期,新芽を5円玉の穴に通して文字通り「金のなる木」とすることが流行し,カネノナルキの通称も定着している。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
昭和などの時期では、よく普通に園芸店などで五円玉を
通した状態の金のなる木が
売られていました。
五円玉を通した状態にする手順は
- 小さな豆粒のような若葉を見つける
- 五円玉をくぐらせて、葉柄のはめる
- 葉身が育って抜けなくなる
- 五円玉がなったように見える
日本での俗称「金のなる木」は、小さな若葉に5円玉をくぐらせて葉柄(ようへい)にはめると、やがて葉身が育って抜けなくなり、葉は数年間落ちないので、これを次々と繰り返せば、5円玉がなったように見えることからつけられた。
出典 朝日百科「植物の世界 5 種子植物」p.228 朝日新聞社 1997.10
TAGS:多肉植物, 育て方, 違い
金のなる木 五円玉と同じカテゴリ
 シェフレラ 葉が落ちる原因
シェフレラ 葉が落ちる原因 レッドロビンにつく害虫
レッドロビンにつく害虫 モンステラ 葉が黒くなる 垂れる
モンステラ 葉が黒くなる 垂れる モンステラにつく虫
モンステラにつく虫 ガジュマルの落葉原因
ガジュマルの落葉原因









